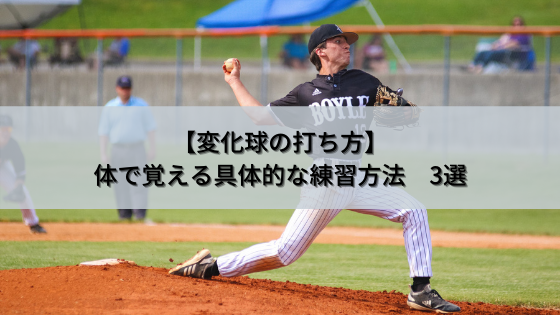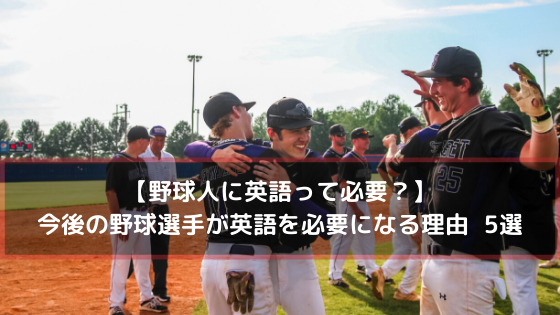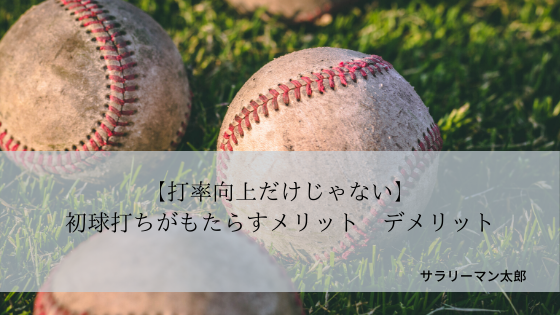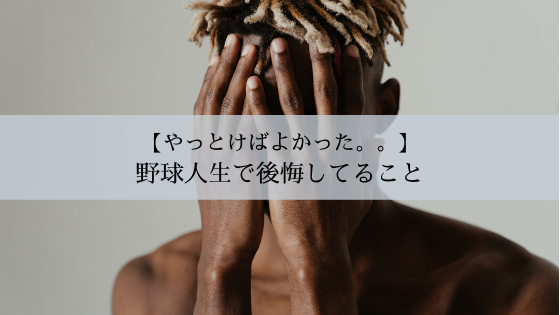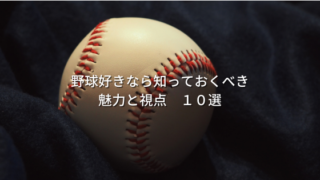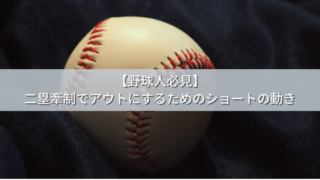そんな選手の悩みを解決できる練習方法をしょうかいします。
大前提として
- タイミングが合っていない
- バットの軌道が合っていない
この2つのどちらかもしくは両方に原因があります。
前者は言うまでもなく
ミットに入ってからバットを振っても当たりませんし、まだボールが来てないのに振っても当たりません。タイミングの取り方は人それぞれです。
足を上げても良し。すり足にするのも良し。ノーステップにするも良し。1番タイミングが取りやすい方法を探してみてください。
どうしてもタイミングが合わない選手は、足の上げ方を変えてみたり、バッターボックスの位置を変えてみたり、バスターで打ってみたりするのもいいですよ。
後者のバットの軌道が合ってない人の典型は
頭が突っ込んでバットの軌道がボールの軌道と点でしか当たらない選手です。
そもそも変化球は落ちてくるボールです。
ストレートの様にバックスピンが掛かって揚力があるボールではありません。
極端な事を言うと
真上から落ちてくるボールを強く打とうとしたら、真下から振り上げた方が1番確率良く当たりますよね。
ノッカーのキャッチャーフライの要領です。
地面と平行なスイングで高いキャッチャーフライを打てるノッカーがいたから紹介して欲しいです。笑
バットの軌道が合わない選手とは、
上から下に落ちてくるボールなのに、自分もさらに下に打ち込む。そんな芸当をしようとしている。と言う事ですね。
じゃあ具体的にどんな練習をすれば変化球が打てるようになるのだろうか?
そんな悩みを抱えている選手に参考にしていただければと思います。
変化球の打ち方を覚える具体的な練習方法 3選
変化球の打ち方を覚える具体的な練習方法は以下の3選です。
- ボールをワンバウンドさせるティーバッティング
- 踏み出し足側にベースを置いて肩のラインをやや斜めにしながらティーバッティングを行う
- 骨盤に上体を乗せたまま行う【低重心ティーバッティング】
これらが明日から取り入れられる変化球が打てるようになる具体的な練習方法です。
それぞれの打ち方をマスターすればどんな変化球にも対応できるでしょう。
とはいえ
いきなり全部をマスターするのには時間もかかりますし、得意と不得意があって普通なので自分なりに
という練習から取り入れて見てください^ ^
それでは早速ですが、具体的な方法を解説していきます。
ボールをワンバウンドさせるティーバッティング
通常はトスをあげる人から投げられたノーバウンドのボールを打つ事が多いと思いますが、ボールを地面にワンバウンドさせてから打つ練習です。
トスをあげる人は安全面を考慮してネットに隠れながら行う事を推奨します。
バウンドさせる事で、ボールがどのように弾むかを見極めて落ちてきた所を打つ練習です。1度バウンドさせる事で、どこに弾むか分からないので不規則性が強くなります。
ワンバウンドしたボールが打てるポイントまで届かなかった場合は打つ必要はありません。
届かずにツーバウンドするような投球はボールですからね。
あくまで自分のポイントまで引き付けて、打てる所まで届いてきたボールに対して軸足を自由に使ってボールを打つ練習です。
ですので勘で打ちにいくのではなく軸足でボールを見極めた後に膝を柔らかく使ってボールの軌道に合わせて打つことができるようになります。
最もシンプルな待ち方でありながら、最も難易度が高い待ち方でもある、全てのボールに対して軸足でボールを見極めるために行う具体的な練習方法です。
踏み出し足側にベースを置いて肩のラインをやや斜めにしながらティーバッティングを行う
肩のラインを真っ直ぐにする事を意識してどうしても頭が突っ込んでしまい変化球が打てない選手は
踏み出し足側にベースを置いて高さを作ることでやや軸足側の肩を下げて、投手を見上げるような意識を持たせる練習方法が有効です。
軸足側の肩を下げる事で、低めの球が死角になり自ずと手を出しにくいボールの待ち方ができるようになります。
記事の冒頭でも述べましたが、そもそも
変化球はストレートよりもボールの揚力が少ないです。
つまり、ストレートに比べると全ての変化球は落ちてくるボールになるので、ややアッパー気味にスイングを仕掛けたほうが、投球の軌道にバットの軌道が合いやすくなります。
この練習方法は頭の位置が残りやすいので同時にトップも残りやすくなります。
さらに軸足に体重を乗せならがボールを見極める事ができます。
結果的に投球の軌道にスイングの軌道が合いやすくなります。
とはいえ、ここまでの話を聞くと、いい事づくめの様に感じますが注意点もありますので以下で解説します。
肩のラインをやや斜めにして打つ事のデメリット
- ヘッドが落ちてインパクトで負けやすい
- 高めのストレートに空振りしやすい
- 顎が上がると目線が動きやすい
これらは踏み出し足にベースを置いて肩のラインを傾けて練習した時のデメリットです。
デメリットとはいっても、あくまでもともと変化球に対して点でしか打てなかったスイングを強制するために取り入れている練習なので、
そこまで気にする必要はありません。
念のため知識として知っておくだけで
「あぁ。今ヘッドが落ちすぎたな」
などの自己分析をやりやすくするために知っておく程度でいいでしょう。
骨盤に上体を乗せたまま行う【低重心ティーバッティング】
それでは最後に体重を平行移動させつつ前でボールを拾って変化球を打つ具体的な方法について解説していきます。
右投げ左打ちの選手が得意なパターンが多い体重を平行移動させつつ前でボールを拾って変化球を打つ方法です。
右投げ左打ちは右手が利き腕なのでとっさに左手を離すことでスイングの奥行きを出してボールに当たる確率を高くすることが容易だからです。
よく聞く
「右手一本で上手く打った」
などという表現は主にこの骨盤に上体を乗せたまま行う【低重心ティーバッティング】で養うことができます。
この動きを体得するための具体的な練習方法を解説していきます。
広くスタンスを取って重心を極力下げます。だいたい自分のバットをしっかりまたげるくらい足を開くといいです。
スタートポジションは軸足に体重をほとんど乗せて、且つ上体は常に骨盤に乗せた状態にします。
そこから手はトップの位置を保ち骨盤に上体を乗せたまま踏み出し足へ体重を並行移動させます。トスをあげる人に低めのボール球を投げてもらい、前でボールを拾うように打ちましょう。
この時の注意点としては、構えから打ち終わりまで上体は常に骨盤の上に乗せたまま行うことが大切です。
上体がマウンド方向に倒れると、バットを落とすスイングはできても拾うスイングが困難となり内野ゴロの山となります。
※めちゃくちゃ足が速い選手は敢えてゴロを打って内野安打を狙うのもありですが。。。ここでは変化球をヒットにするための方法論として捉えてください。
タイミングをずらされてしまっても相手の思惑通りにゴロにしないために有効な練習方法です。
ですが、この練習もまたやりすぎしまうと悪い癖がついたり、状態を悪化させてしまう危険性もあるので、以下でデメリットについても触れておこうと思います。
補足:体重を平行移動させつつ前でボールを拾って変化球を打つデメリット
- 低めのストライクゾーンが広くなりがち
- 体重がボールに伝わりにくく強く振りにくい
軸足のパワーを使った打ち方といよりも上体の柔らかさや器用さで変化球に対応する打ち方のため、成功体験を重ねると味をしめて全部この方法でヒットを狙うようになります。
そうすると自分では気づかないうちに低めのストライクゾーンが広くなりがちです。
「もっと低めまで拾える」と欲をかくと、軸足に乗せたパワーをボールにぶつける本来の打ち方を見失うこともあるので注意しましょう。
また、踏み出し足に体重を移動させながらスウェー気味に打つので体重がボールに伝わりにくく強く振りにくいので変化球を長打にするには適さない打ち方と言えます。
この辺のデメリットも頭に入れた上で練習していきましょう。
変化球の打ち方を体で覚える具体的な練習方法 まとめ
いかがでしたでしょうか。
本記事のまとめとしたまして、内容をおさらいします。
- ワンバウンドのティーバッティング(軸足を折ってボールをすくい上げて変化球を打つ)
- 踏み出し足側にベースを置いて肩のラインをやや斜めにすしがらティーバッティング(軸足でボールを見て変化球を打つ)
- 骨盤の上に状態を乗せたまま低重心のティーバッティング(踏み出し足に体重を平行移動させつつ前でボールを拾って打つ)
以上になります。
それぞれの練習で得られるメリットや偏った練習によるデメリットをしっかりと頭に入れつつ、変化球もしっかりとヒットにできる打者にステップアップしていきましょう。