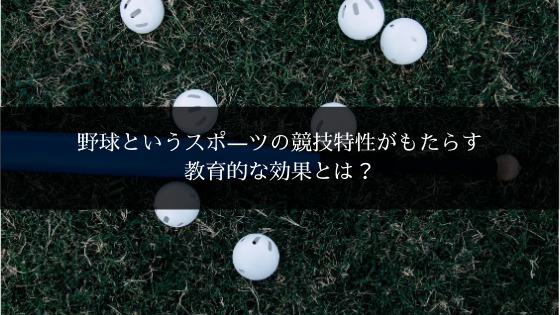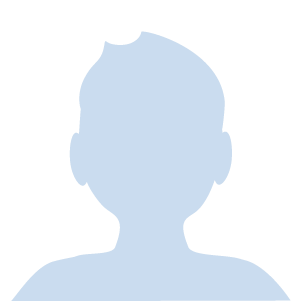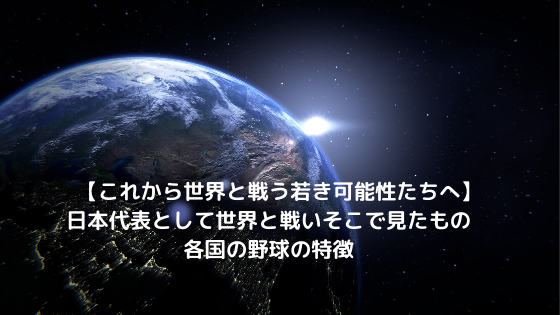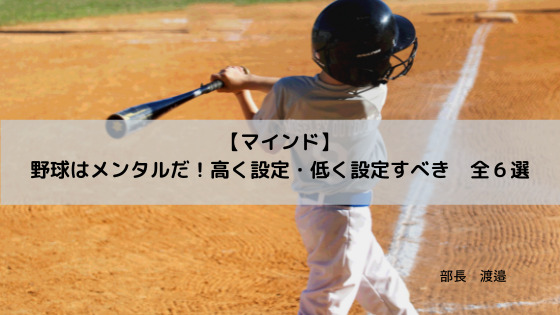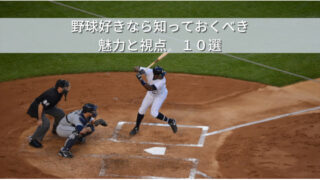本記事では、世の中の球児の保護者の方が気になる部分かもしれせん。
特に野球経験のない親御さんが感じることがい多いかと思います
今回はこのことについて記述していきたいと思います。
野球というスポーツの競技特性がもたらす教育的な効果とは?
野球が及ぼす教育的な効果は以下のものが代表的なところになります。
ざっと列挙しただけでもめちゃくちゃありますね^^
興味があるチャプタへ目次から飛んでも構いませんので是非目を通してみてください^^
それではやっていきましょう!
主体性が磨かれる
野球というスポーツは投手の投球数がおおよそ100〜120球です。多くても150球前後ではないでしょうか。そん間に監督が選手に指示を出して選手を動かすのは何球くらいかご存知でしょうか?
実際に監督の指示で動くのは1試合で5球〜10球。多いチームでも15球程度しかありません。
つまり、そのほかの100球以上は打者と投手の間で、「打つのか打たないのか」ストライクゾーンで勝負するのか、しないのか」などは、選手自らが判断してプレーする必要があります。
監督やコーチからのサインに対して求められた仕事に答える部分と
主体性を持って自らの決断で動く部分の両方が求められるというわけですね^^

数字による成績の分析、課題の明確化
野球をやるうえで、日ごろの練習で数字と向き合うことが多々あると思います。
試合で例えれば、打率、防御率、ホームラン数など沢山ありますよね^^
実際には試合の成績の数値化だけでなく、日ごろの練習の中でも50m走のタイムだったり打球速度を記録するチームもあるかと思います。
自分の成長を数字で目にすることは非常に大切で、
「なんとなく球が速くなったなぁ」
というような感覚ではなく数値で実感することでなぜ数字が向上したのかフィードバックがしやすくなるからです。

PDCAの習慣化
一球、1プレー、1打席ごとに結果が出ます。1試合の中で何度も
自分が考えた作戦(P)を実行(D)してみた結果を検証(C)し、改善(A)する
これを繰り返します。行き当たりばったりの成るように成るさ精神だけではいい結果は生まれません。常に頭を働かせながら良い結果を手繰り寄せるためにPDCAを繰り返す習慣スポーツ以外でも大きな武器となることは間違いありません。
相手選手の洞察、観察力、プランニングの向上
野球は打順が順番通りに回って来ます。
自分が打席に来るまでに相手の投手の状態、バッテリーの攻め方、得な球種(またはコース)を見極めるのに十分な時間が用意されています。
先ほど述べた「PDCA」のPにあたる部分を野球の間という競技特性を利用して
向上させていきましょう。
守備においても同じことが言えます、投手が投げるまでの間に時間があるのでその間に飛んでくるであろう方向や相手打者が狙っているバッティングを洞察し予測しながら先回りして備えましょう。

バックアップの重要性
「バックアップ」それは
大抵の場合起きないけれど、もし起きてしまったら大変なことになるので備える事です。
打球が自分のところに飛んでこなくても意外とやることがあるのが野球です。
バックアップはその最たる例で、バックアップをしっかりすることによって仲間が思い切った送球をすることが可能になり、好プレーに繋がるものです。
万が一起きてしまっても大丈夫という態勢を整えておく週間は野球以外においてもとても大切な考え方です。
切り替えの速さが求められる
野球は失敗のスポーツですから、プレーする中で時にはミスを犯してしまうこともあるかと思います。
しかし失敗したことを後悔したり引きずったりしても試合はどんどん進んでいきます。
なぜミスしたのかを反省することは大切ですが、すぐに切り替えて「次こそは!」というマインドでプレーすることが求められます。
試合の中で起きた反省は試合後にすればOKですので、試合が終わるまでは
次!次!どんどん切り替えてプレーしていきましょう!
ルールを守る意識とルールを駆使する意識
野球のルールブックを読んだことがある人ならわかっていただけると思いますが、野球のルールって
まぁ多い。そして難解!ざっと2000以上のルールがあります。
という声も聞こえてきそうですが、
できる限りしっかりとルールを覚えることで冷戦な判断と、ルールを最大限に利用したプレーができるようになります。
野球は数あるスポーツの中でもダントツにルールが多く複雑です。そのルールに基づいて判断、実行することが求められます。
状況の確認と情報の整理
野球はプレーとプレーの間に時間「間」があります。
皆に平等に与えられたその「間」をどう使うかで、結果は大きく異なりなす。
そりゃボケーっと空を飛んでる鳥を眺めているより、次のプレーに対する頭と体の準備を怠らずに取り組んでいる選手のほうが成長率が違うのは当然です。
先ほど述べた事前の準備という話と類似しますが、時間の使い方の重要性を学ばせてくれることも野球の面白いところではないでしょうか^^
時間の使い方が大切だということは当たり前のようですが理解しきれていない人も多くいるのが現状なんですがね^^;
危険が多い「危機管理能力の向上」
どのスポーツもそうですが、怪我は付き物です。
正しい体の使い方、栄養。休養のバランスが崩れていてはつまらない怪我を招く原因になります。
プレーの中で相手を怪我させてしまうこともあるかもしれません。どうしても防ぎようがない怪我も確かにありますが、怪我を未然に防ぐための体のケアや休養が大切だということは技術を向上させるのと同じくらい重要だということを学ばせてくれます。
そうすることによって自己管理能力の向上も期待できます。
環境の変化への対応
土のグラウンドだったり、人工芝のグラウンドだったり、天然芝だったり、広い球場、狭い球場などその日その日で状況が変わるものから
太陽の位置、天候の急変、風向きなど試合中や練習中にも環境というものは目まぐるしく変わります。
ここではざっくりとこの程度にしておきますが他にもめちゃくちゃいっぱいあります。

専門性、自分の持ち場への責任感が生まれる
野球は各ポジションで役割が明確に変わります。
言い換えれば「個性を生かす場所が複数準備されている」とも言えるでしょう。
ポジション1つ1つが専門職と言ってもいいでしょう。そのため任されたポジションで自分の能力を発揮するチャンスがあるはずです。
常に自問自答します。団体競技とはいえ、各ポジションを守るのは一人だけです。責任感をもって役割を全うする精神が養われます。
探究心が磨かれる
飛距離、ベースランニングタイム、球速へのこだわりなど
「少しでも速く」「少しでも遠くへ」といった純粋な欲求が出てきます。その欲求を満たすために、どんな打ち方がいいのか、どんな投げ方がいいのか、自分に合ったスタイルは何かなど、自身の中に秘められている探求心が育まれます。
その過程で、失敗や成功を繰り返し成長をしていけるでしょう。
また、「○○選手みたいな選手になりたい」というような憧れが生まれ、その選手に少しでも近づくための努力が選手を大きく育ててくれます。
今では、様々な情報がインターネットを介して手に入れられる時代になりましたので情報の取捨選択を上手にしながら階段を上っていきましょう^^

野球というスポーツの競技特性がもたらす教育的な効果とは? まとめ
いかがでしたでしょうか、最後に本記事をおさらいすると
以上になります。
野球というスポーツが教えてくれるこれらの部分をしっかりと人間的成長につなげて
スケールの大きなプレーヤーを目指しましょう^^